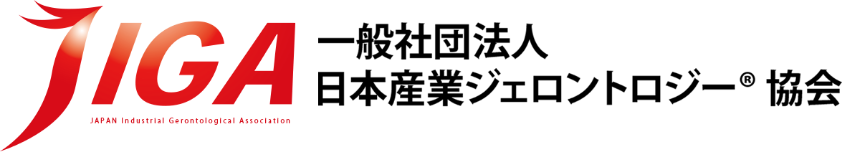ジェロントロジーと産業ジェロントロジー
- ホーム
- ジェロントロジーと産業ジェロントロジー
ジェロントロジーとは

ジェロントロジー(Gerontology)は「老年学」「加齢学」と訳されています。ギリシャ語の「高齢者」の意味を表すGerontに、「学」を表すologyがついた造語です。
加齢による人間の変化を、心理・教育・医学・経済・労働・ 栄養・工学など実に様々な分野から学際的に研究する学問です。今までは、主に、医療・福祉・美容という分野で生かされてきました。
「産業ジェロントロジー」とは、ジェロントロジーの研究成果を企業の人材マネジメントに生かす取り組みです。当協会では、世代間の精神的・肉体的な違いに注目し、能力開発や労災防止、職場環境づくり、また、それらを推進する人材の育成と資格認定、研究活動に取り組んでいます。特に、アドバイザーの養成・資格認定は、多くの企業の方から賛同・支持をいただいています。「超高齢社会の日本においては、一社に一人、産業ジェロントロジーアドバイザーが必要だ」という意見もいただいています。
高齢社会の必須科目「産業ジェロントロジー」
私たちは、いくら努力しても自分の年齢以上に年を重ねることができません。育児は、子供がいない方でも自分の幼少時を思い出すことにより、イメージすることができますが、定年退職や、親の介護、身体の老化現象はそうはいきません。
よって「加齢とはどのようなことか?」について学ぶ必要があります。
例えば、モチベーションの低下。気持ちの問題ととらえられがちですが、それだけが原因ではありません。高齢期になると疲労の回復が遅くなるため、やる気があっても行動が伴わなくなります。仕事の指示も急な出来事に対応することが苦手になるので、事前に準備できるように指示を出してあげることも必要です。このような特徴を若い世代が学ぶことにより、異世代間の歩み寄りが生まれます。また、中高年世代の方たちの自己管理や、気づきを促すことに役立ちます。
当協会の目標は、すべての日本企業の新入社員教育に「産業ジェロントロジー」を取り入れていただく事です。
「シニアの結晶性能力を生かす」
高齢期になっても衰えない能力として「結晶性能力(知能)」があります。これは、私たちが長年にわたった経験、教育や学習などから獲得していくものです。
人生100年といわれる今、私たちが効率よく、生き生きと働き続けるためには、この「結晶性能力」を活用することが必要です。しかし、高齢者自身の努力だけでは、「結晶性能力」を生かすことは不可能です。働く場づくり、異世代のサポート、使いやすい機材など、様々な要素が必要です。
「産業ジェロントロジー」は、シニアの結晶性能力を仕事の場で生かすために、多様な視点からの取り組みをします。なお、新しい情報を入手したり、記憶する能力を「流動性能力(知能)」といいます。こちらに関しては、若年世代の方が長けています。世代間の役割分担を考えることも、「産業ジェロントロジー」の一つです。
産業ジェロントロジー教育の必要性
私たちは、いくら努力しても自分の意志で年を取ることができません。よって「加齢とはどのようなことか?」について学ぶ必要があります。特に、働くうえでどのようなことが起きるのかということを考える「産業ジェロントロジー教育」は、高齢社会の必須科目として私たちはとらえています。
例えば、モチベーションの低下。気持ちの問題ととらえられがちですが、それだけが原因ではありません。高齢期になると疲労の回復が遅くなるため、やる気があっても行動が伴わなくなります。仕事の指示も急な出来事に対応することが苦手になるので、事前に準備できるように指示を出してあげることも必要です。このような特徴を若い世代が学ぶことにより、異世代間の歩み寄りが生まれます。また、中高年世代の方たちの自己管理や、気づきを促すことに役立ちます。